
どうも、サンモトです。
今回はタイトルの通り『扶養』に関することで、私が悩んだ時の事を記事にしました。
世の中の働く人、特に会社勤め(サラリーマン)の人なら『扶養』という言葉を知っている人は多いと思いますが、
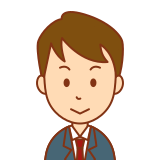
「『扶養』ってどういうものですか?」
と聞かれて、わかりやすく説明できるでしょうか?
私も少し前までは

「家族を『扶養』に入れられると色々とお得らしいね(よくわからないけど)」
「手続きとかも面倒そうだし、自分には関係ないかな(-_-)」
ぐらいの認識でした。
扶養は不要、といった感じです(-_-)
しかし昨年の2020年は私やその周りでも色々と変化があり、幸か不幸か、『扶養』に関して学ぶ機会が出てきました。
その変化というのは、一緒に暮らしている父が自営業を廃業したことです。

「父が廃業した理由などは今回関係ないので触れませんが、重要なのは廃業した事により『父親の収入が減少した(無くなった)』という事実です」
「ちなみに母は専業主婦で、父が働いている間は父の配偶者という立場で確定申告の控除枠を利用していました(配偶者控除というやつです)」
「しかし、仕事を辞めた後では当然その手続きはできなくなります(T_T)」
「父が正式に届け出をして廃業したのが2019年の年末なので、2020年からは事業収入がゼロで年金の一部だけを貰っているという状態になりました」
「母はまだ年金が貰える年齢に達していないので、当然収入はゼロです」
この事実に私が気づいたのは、会社から年末調整の書類が渡される11月頃でした。

「ひょっとして今の状況なら、両親は私の『扶養対象』というものになるのでは・・・?」
そう思いつき、私は年末調整のタイミングで会社の総務部に相談をしました。

「すみません、今年から両親を『扶養』に入れたいんですけど・・・どういった手続きをすればいいのですか?」
その時、総務の人にはこう聞かれました。
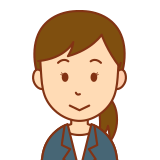
「それはご両親を『社会保険上の扶養』に入れたい、ということですか?」
聞いた事がない単語に一瞬頭が呆然としました。

「社会保険上・・・?」
「『扶養』っていくつもあるのか・・・?」
ここで私は『扶養』には2種類ある、ということを知りました。
その後なんだかんだと時間はかかりましたが、無事に両親の扶養申請を終えて、この記事を書いています(-_-)
同じように『扶養』について悩むことになる人がいるかもしれないと思い、以下に私なりに調べたことをまとめてみました。
参考になれば嬉しいです。
扶養には『税法上の扶養』と『社会保険上の扶養』がある

※私は専門家ではないので詳しく解説したり、本当に正しい事を言えているのかはわかりません。
※あくまで私なりに嚙み砕いた説明という認識でお願いします(-_-)

「そもそも扶養というのは、家族や親族から経済的援助を受けることをいいます」
「例文として『妻が夫の扶養に入る』などの使われ方をしますね」
「その扶養を受けている人の事を被扶養者と呼び、主に扶養者の収入によって生活をしている人のことです」
「会社員の人の場合、生計を共にしている家族を被扶養者にできればお得なことが多いため『扶養に入れた方が良い』『扶養した方がお得だ』という認識が一般的になっています」

「確かにその認識は間違いではないのですが、実際に扶養の手続きをする際は気を付けなければならない点がいくつかあります」
「一つは、扶養には『税法上の扶養』と『社会保険上の扶養』があって、それぞれ出来る内容が違うこと」
「もう一つは、『税法上の扶養』と『社会保険上の扶養』では扶養対象となる家族等の範囲が異なることです」
「その違いがあるため一口に『扶養する』といっても出来る範囲が変わってくるし、両方できる人もいれば片方しかできない人もいるという場合が出てきます」
「私もそうでしたが、この『税法上の扶養』と『社会保険上の扶養』をひとまとめにして考えていると、実際に手続きをしようとした時に戸惑うと思います」
「その違いについては次の項目で解説していきます」
『税法上の扶養』と『社会保険上の扶養』の違いと申請方法
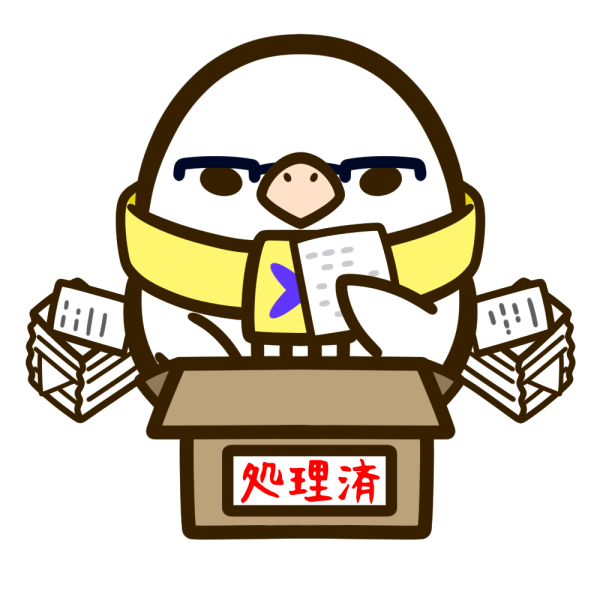
上記でも触れましたが、『扶養』には『税法上の扶養』と『社会保険上の扶養』の二種類があります。
この二つの『扶養』の特徴はそれぞれ以下のようになります。
- 税法上の扶養・・・家計を主に支える人が住民税や所得税の控除を受けられ、納める税金の金額を抑えられる。扶養控除のこと。
- 社会保険上の扶養・・・家計を主に支える人の勤め先の社会保険(健康保険・厚生年金など)の被扶養者になる。自分で健康保険料などの社会保険料を納めなくてもよい(扶養者が代わりに払うから)
こんな風にそれぞれ内容と扶養対象の範囲が変わってきます。
内容に関してはこう書かれてもピンと来ない人も多いと思うので、

「税法上の扶養は納税する本人(扶養者)がお得になる」
「社会保険上の扶養は納税する人の扶養に入っている人(被扶養者)がお得になる」
程度の認識で問題ないと思います(-_-)
二つともできれば、家計全体で見ればお得になるのは間違いありません。
扶養対象の範囲に関しては、以下のHPが参考になると思います。
※自分が加入している健康保険組合は保険証で確認できます。

「被扶養者の申請方法ですが、会社員の人なら二つとも会社(総務部)に必要書類を提出するだけです」
「『税法上の扶養』申請なら年末調整の時に渡される書類に必要事項を書いて提出すればOKです」
「『社会保険上の扶養』申請なら総務に書類を手配してもらい、別途必要書類と併せて提出すれば会社を経由して日本年金機構に提出されます」
「会社員の人は基本的に会社の総務部とのやり取りだけで済むので比較的楽です(-_-)」
※自営業の人に関してはまた変わってくるので、申し訳ないのですが私は調べていません(自分に関係しないことまで調べる余裕がなかったので)

「しかしその必要書類という部分がネックで、書き方がわからない部分があったり、すぐに用意できない書類だったりすることがあるため、申請の段階まで行くのに思っていたより時間がかかる場合もあります」
「私の場合は勤めている場所と申請手続きをしてくれる本社の総務の場所が離れていたため、書類を送ったり送られたり、電話で確認したりされたりを何度か繰り返すハメになりました(-_-)」
「なので、思い立ったらすぐに行動に移すことをオススメします」
「結局のところ総務部とのやり取りが円滑なほどスムーズに処理できるので、最初から全部人任せにするのではなく自分である程度調べることが大切です」
「わからないことがあれば積極的に聞くということをすれば問題なくできると思います」
「書き方を間違えたり、申請が受理されなかったりしても特にペナルティなどはないので『いけるんじゃないかな?』と思ったらやるだけやってみる価値はあると個人的に思います」
まとめ

以上、『“扶養”は2種類ある、と知って頭が混乱した話』でした(-_-)
門外漢で未だにわからないことも多い私が書いた記事なので、説明不足だったりわかりにくい部分もあったと思いますが、ご容赦ください。
私も今回の件で自分が知らない・わからないことの多さと、言葉で上手く説明することの難しさを実感しました。

「ここはこういう表現で合ってるのかな・・・?」
「こういう解釈で問題ないだろうか・・・?」
ネットサーフィンで情報を漁り、集めた情報を頭の中で整理したり、四苦八苦しながら一人で黙々と作業していると何度も途中で投げ出したくなる気持ちになりました。
それでも何とか記事に出来たのは

「こんな面倒な事を自分から取り組んで解決できたんだ!」
という自信と達成感が得られたのと

「同じような事で悩んでいる人の参考になったり、後押しになれたら良いな」
と思えたからです。
今なら同じような悩み・疑問を持っている人に対して共感でき、真摯に対応できる気がします(-_-)
この気持ちを忘れずに、どこかの誰かにとって
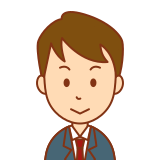
「役に立つ情報だった♪」
と思って貰えるような記事を書きたいと思います。
この記事を読んでくれた人が、少しでも自分の生活を良くするキッカケを掴んでくれたら嬉しいです。
おわり
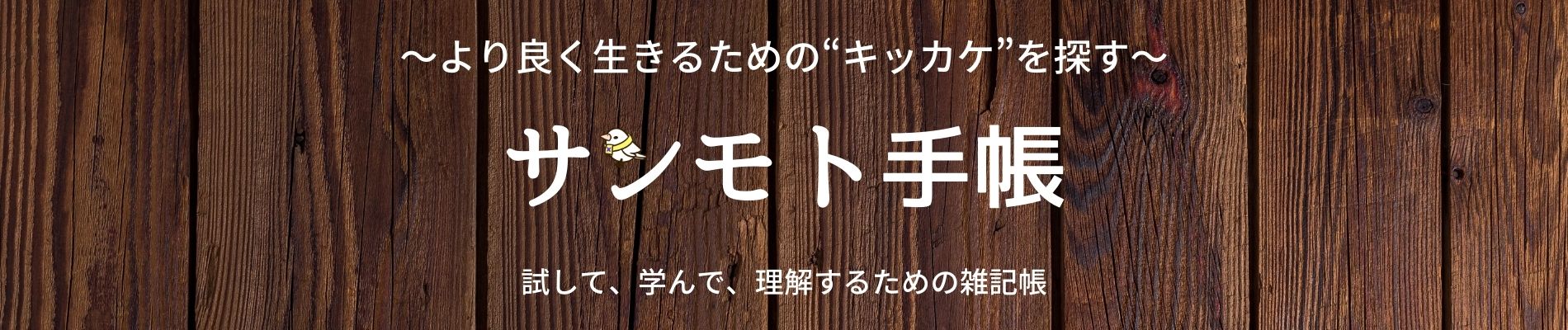



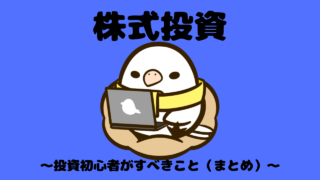






コメント